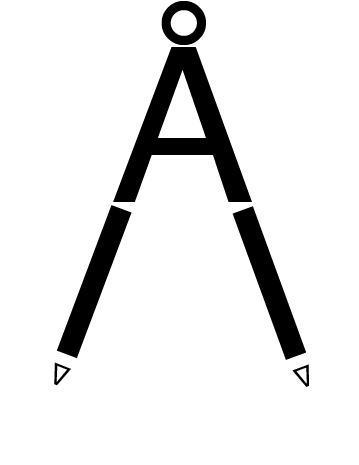2歳の子どもに創造性とは何かを教わった話
突然始まったブログ。これっきりかもしれない。
ロンドン北部の郊外の自宅には、2歳の子どもがいる。今年に入っていっしょに過ごす時間が増え、順調に夫婦の時間が奪われ、風邪だの道端の犬のウンコをつかむだの、毎日が事件だ。しかし悪いことばかりではない。この2歳児の遊んだ後を注意深く観察していると、大人が創造性と呼んでいるものが何なのかがとてもよく分かる。
【親というのは、概ね創造的ではない】
すべての親は、子どもに安全かつ自分で勝手に遊んでもらいたいという虚しい願い事をする。
無駄である。
断言できるが、この願いは決して叶うことはない。 そして親は、子どもに創造的に育ってもらいたいといろいろな仕掛けを用意する。しかしこれも、ほとんどの場合は目的の通り使用されることはない。
たとえば「知育玩具」には強力な磁石が使われている場合がある。もちろん子どもはその知育玩具を、決められたルールを守って遊ばない。そればかりか、もっとも置いてほしくない場所、パソコンなど、磁力に弱い電子機器のそばにそっと置いておく。親が絶望感溢れる表情でそれを発見するとき、彼女らはまるで天使のような顔でぐっすりと眠っている。
無駄なのである。
親は「ひとりで創造的に育って欲しい。そうなってくれれば言うことなしではないか」というよく考えてみれば非常に創造的ではないことを願いながら、「うーんどうしたものか」と、決して思う通りにならない子どもに頭をかかえて日々を過ごしている。これがずっと続くと言っても過言ではない。そして僕ら夫婦もそのひとりだ。
【創造性とは、裏切りである】
英語で既成概念を捨てて考えることを「Out of the Box」と表現する。しかるに、彼女の等身大サイズのダンボール箱を与えてみた。まんまである。まったく想像力を欠いた提案だったが、これが非常に大ヒットした。朝の9時から遊び始め、だいたい4時間くらいは熱中していた。2歳の子どもを持つ人はこれがカール・ルイス並に度肝を抜く記録であることが分かるだろう。たとえは古すぎるにしても、だ。
さて、これがその現物写真だ。およそこれが何なのかは分からない。おそらくだが、家とスケッチブックの中間のような存在だ。 最初このダンボール箱を与えたときは「切り抜きゲーム」をしようと考えた。つまり、子どもにクレヨンで何か描いてもらい、それを僕が切り抜くというゲームだ。カッターで僕がクレヨンで描かれた正方形をささっと切り抜いてみせるとさっそく子どもから、きらめく笑顔で
「しゅごい!(すごい!)」
が出た。 しかし、いざクレヨンを渡してみると、ぜんぜん切り抜いて欲しいとか思わない。自分の描けるもの(「ぐるぐる」と呼ばれる前衛的な画像)をひたすら熱中して描きまくる。目的は、ない。
さっきの「しゅごい」は一体何だったのか。このように創造性というのは、さっきまで賛同していたのに、突然裏切ったりする。理由は、ない。
【創造性は、秘密である】
箱というのはセクシーなメタファーである。小泉ナントカではないが。バラス・スキナーという名のアメリカの心理学者がいた。彼は箱を用いてとある実験装置をつくった。その箱の中には、引くとエサが出てくるレバーがついている。ここにラットを入れると、ラットはいつしかレバーを引けばエサが出てくることを学習する。そしてラットは何度もレバーを引き、エサを手に入れる。彼はヒトもラットも、現在の行動を決定づけているのは「過去の経験」だと考えていた。そして小さな箱の実験で、ラットは過去の行動の結果「良い思い」をしたことを繰り返すことを確かめた(強化理論)。この箱を「スキナー箱」と言う。
まあ、スキナー箱とか知ったこっちゃない。
子どもをしばらく放っておくと、ダンボール箱の中に入っていた。僕が開けた正方形は窓として活用されていた。めずらしくおとなしいなと思っていると、箱の中から小さな唸り声が聞こえてくる。ウンコである。 少し前からウンコをするときは暗くて閉鎖された場所に入るようになった。ブランケットにくるまったりして自分のプライベート空間をつくってウンコをするようになった。おそらく羞恥心の現れなんだろう。僕たちがトイレに行くとき、限定的なプライベート空間に入るのを毎日見ているので、それを自分なりに再現しているのだ。その行動の結果、落ち着いた。それがかくして繰り返されたのだ。最臭的に箱の中で繰り広げられる強化理論である。
ウンコとは、おおいなる秘密である。特殊な人を除いてはウンコをシェアしたりしないし、「いいね」したりもしないものだ。 臭いしな。
【創造性とは、反逆である】
その次の瞬間には、ダンボール箱はソファーの上に乗り上げて、中でライトをつけて完全に家化していた。二歳児はときに巧妙である。
午後になるとさすがに飽きたようでダンボール箱はライブが終わったライブハウスみたいに打ち捨てられていた。彼女は僕があけた、窓として活用されていた穴からは中に入り、ダンボール箱の一部は破壊されている。よく見てみると、僕が一番丁寧にあけた穴には一切手をつけず、もうひとつの穴は窓やら突入に使われて崩壊している。
このように、親が「よかれ」と思ったことになど、子どもはまったく用はないのだ。なぜならそれらは非常に創造性を欠いたおせっかいであり、彼女らの嫌悪するものだからだ。
創造性というのは、常に非創造性に対する反逆である。きれいに残ったダンボールの穴にその真理の一片を見た気がした。