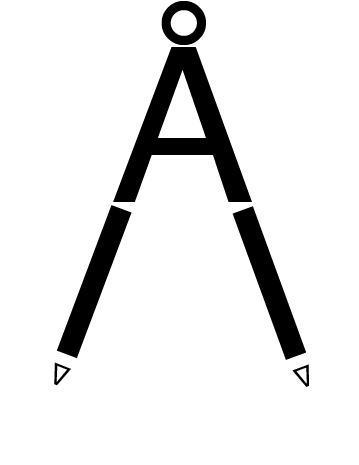WIRED VOL.56
Quantumpedia その先の量子コンピューター
従来の古典コンピューターが、「人間が設計した論理と回路」によって【計算を定義する】ものだとすれば、量子コンピューターは、「自然そのものがもつ情報処理のリズム」──複数の可能性がゆらぐように共存し、それらが干渉し、もつれ合いながら、最適な解へと収束していく流れ──に乗ることで、【計算を引き出す】アプローチと捉えることができる。言い換えるなら、自然の深層に刻まれた無数の可能態と、われら人類との“結び目”になりうる存在。それが、量子コンピューターだ。そんな量子コンピューターは、これからの社会に、文化に、産業に、いかなる変革をもたらすのだろうか? 来たるべき「2030年代(クオンタム・エイジ)」に向けた必読の「量子技術百科(クオンタムペディア)」!
Contribution
interview and writing:
Mikhail Lukin / Joshua and Beth Friedman University Professor Co-Director of the Quantum Science and Engineering Initiative, HARVARD UNIVERSITY
Peter Brabeck-Letmathe / Chairman of the Board of Directors at GESDA, Vice-President of the World Economic Forum
Tim Smith / Coordinator at Open Quantum Institute (CERN)
Marianne T. Schörling / Open Quantum Institute Capacity Building Lead, Senior Program Manager at GESDA
Alexandra Bernasconi / Application Project Manager of the Open Quantum Institute
Pierre Desjardins / C12 CEO
David Hayes / Director of Computational Design and Theory at QUANTINUUM
ここ数年間は量子について、本当にいろんな仕事や場所で見聞きしてきた。そのたびに驚かされてきたのは、僕たちはこの宇宙についてどれだけ知り得ているのか、ということだった。そしてその知り得ていることは、僕たちが思っているよりも、遥かに深いのかもしれない。量子力学の深淵にふれるたび(もっともそれらは、とても難解なことばかり)そう思う。
そして量子というテーマにふれるたび、人間の知性とはそもそも何なのかを考えてきた。この世界のものごとを極限にまで小さなスケール、粒子のサイズで見ていけば、それは観測されたときに、ランダムに決まる。歴史的にも、さらに言えば僕たちの“感覚的”にも受け入れられないような転換点を、現代物理学は前世紀に迎えていた。そして、いまはこの原理すら活用して、この宇宙そのものを根源から計算しようとしている(量子コンピュータ)。
僕たち人間の知性はこの途方もないことを発見し、それによって計算機をつくる。でも、それが何のために生まれ、人間にとって何になるのか、実はこの世界の誰一人として、よく分かっていないのだ。
ぼくが量子に惹かれ続けるのは、この不思議にある。そして地球の最前列でそれに触れていたいということが、僕の望みだ。
今回のWIREDでは、量子コンピュータのダークホースである中性原子方式で、数多くのブレークスルーを生み出してきたハーバード大学の物理学教授ミハイル・ルーキンへのインタビュー記事を担当。これも本当に、ひさびさに論文とにらめっこの作業だったのだけれど、彼をシンギュラリティ(技術的特異点)のドアをノックしている数人の人類のひとり、というイメージでストーリーを書いてみた。正直言って難解なのだけれど、そのノックの音や質感を、できるだけ忠実につかんでもらえるように、無骨なサイエンスのファクトをごりごりと詰め込んだかっこいい記事になっている。
もうひとつは、CERNにあるOpen Quantum Instituteについて、詳細なインタビュー記事を書いている。『量子コンピュータに永世中立は築けるか?』というタイトルなのだけれど、これは量子コンピュータにおけるガバナンスについてとても深い洞察がある内容になっている。現在のコンピューティングは非常にバランスが悪い。つまり、この世界のビッグテックはアメリカに集中し、世界でもっとも多くのデータを持つ政府は中国だ。量子コンピュータの革命前夜の、ガバナンスの在り方をOpen Quantum Instituteに追った。
そして最後に。
宇多田さんとはCERNで本当にいろんなことをお話させていただいたのだけれど、はじめて会った宇多田さんは、自分の心にずっといた宇多田さんと、まったく同じ人でした。
Knockin’ on singularity’s door ミハイル・ルーキンという革命
量子誤り訂正。その機能化は、量子コンピューターが現実のテクノロジーとして広く展開されるための決定的な条件だ。情報の精度を担保し、規模の拡張性を保証するこの仕組みを、具体的に中性原子アーキテクチャに実装する──その方向で現在、もっとも注目されているのがミハイル・ルーキンである。
ハーヴァード大学で理論と実験の双方をまたぎながら研究を進めてきたルーキンは、1990年代末から中性原子方式に取り組んできた。レーザー冷却によって温度を極限まで下げ、磁気光学トラップと光ピンセットを用いて原子を制御するこのアプローチは、長らく「理論的には有望だが実現は難しい」とされてきたが、2016年以降の技術革新によって状況は大きく変わった。
彼と研究グループは、原子を高精度で配列させる動的光ピンセット技術を開発し、計算に適した構造の安定生成に成功。さらに、リュードベリ状態を活用することで量子ビット間の相互作用を制御し、高精度の量子ゲート操作が可能になった。これにより、中性原子方式が従来の主流アプローチに対抗しうる現実的な選択肢として台頭してきた。
2023年には、280個の物理量子ビットを用いて複数の論理量子ビットを形成し、それを制御可能なプロセッサとして動作させる実験に成功。量子もつれを使ったエラー検出と修正を実現し、量子誤り訂正の実装における重要な成果を示した。
ルーキンは、こうした進展を「予想されたもの」だと捉えている。中性原子アーキテクチャがもつ理論的な利点は、すでに25年前の時点で明らかだったからだ。しかし、それを具体的な実装に結びつけるには、制御ツールの着実な開発が不可欠だった。
現時点での課題は、ツールのスケールアップにある。現在の装置は、量子化学や物性、核物理といった応用分野で期待される大規模な計算にはまだ対応していない。だが、ルーキンはその可能性を否定しない。論理量子ビットによる処理や誤り訂正はすでに実現段階に達しており、「かつては未来の話と思われていた技術が、すでに実験室のなかで動きはじめている」と彼は語る。
特異点はまだ先にある。しかし、それを前提にした議論と実装が、すでに始まっている──それが、ルーキンの現在地である。
Toward Permanent Neutral Technology: 量子コンピューターに“永世中立”は築けるか
ジュネーヴのCERN──この宇宙を記述する最深部の法則が探求される場所に、2024年、「Open Quantum Institute(OQI)」が設立された。科学外交財団GESDAとスイスの金融機関UBSの支援のもと、CERN内部に立ち上げられたOQIは、量子コンピューターの社会的ユースケースを探り、技術の民主化と分散化を主軸に据えている。
量子計算は、新薬の設計から社会システムの最適化まで、今後の地球規模課題に対する解決の鍵となりうる。だが、ハードウェアの構築と同様に重要なのは、それをどう「誰のために使うか」だ。OQIは、科学的中立性を基盤とした「科学外交(Science Diplomacy)」の実践を通じて、量子コンピューターを特定の企業や国家の利害から切り離し、グローバル・パブリック・グッドとしての道を模索する。
OQIが実践するのは、単なる政策提言ではない。量子コンピューターを使ったSDGs関連の応用シナリオを開発する一方で、WFP(世界食糧計画)や複数のグローバル南諸国との連携による「量子ハッカソン」も展開。これにより、発展途上地域の研究者が自身の地域課題に量子的手法で向き合うための実装基盤を整備している。活動は教育・人材育成にも及び、インターンシップや研修制度を通じて地域エコシステムの構築も進められている。
OQIの設立背景には、インターネット黎明期に見られた「開かれた技術」が、やがてビッグテックによって独占され、情報の偏在と支配構造を生み出したという歴史への反省がある。量子技術は、計算力のスケールの観点から見ても、既存の権力構造を大きく凌駕しうる。ゆえにこそ、その「公共性」を最初から組み込む必要がある。OQIの掲げる「オープン」は、研究手法ではなく、設計思想そのものを指している。
同時にこれは、CERNという場所の意味を再定義する試みでもある。粒子加速器のある地下では宇宙の起源が探られ、地上では科学を通じた地政の再構築がはじまっている。21世紀の民主主義は、計算リソースをどう分配し、誰のために最適化するかという問いを避けては通れない。その入口として、OQIの取り組みは確かに機能しつつある。
Different strokes for different folks:Qubitに首ったけ 気まぐれな“アイツ”と悪戦苦闘の開発者たち QUANTINUUM
量子コンピューターと生成AI、その交差点を具体的な技術として提示しはじめた企業のひとつがQuantinuumだ。米コロラド州に拠点を置き、イオントラップ方式による量子ハードウェアの開発を軸に、アーキテクチャから応用領域に至るまでを一貫して手がけている。
2025年2月には、生成AIと量子計算を組み合わせた「Gen QAI(Generative Quantum AI)」を発表。創薬や金融における複雑な予測モデリング、ロジスティクス最適化といった用途を想定し、同社の量子コンピューター「H2」で生成したデータがAIモデルの訓練に用いられている。ここで量子計算は、単なるアクセラレーターではなく、AIそのものの基盤条件を変える可能性のある「構成要素」として機能しようとしている。
Quantinuumの量子ハードウェアは、イオントラップ方式を採用している。特徴は、コヒーレンス時間の長さと精密な量子ビット制御のしやすさにある。加えて、QCCD(Quantum Charge-Coupled Device)と呼ばれる独自アーキテクチャにより、イオンの並べ替えと移動を可能にし、スケーラブルな設計に対応している点も注目に値する。
現在開発中の次世代量子プロセッサ「Helios」では、二次元的な構造と“ジャンクション”と呼ばれる交差点を導入し、並列処理と高精度な量子ゲート操作の両立を目指す。H2に比して1兆倍の性能が見込まれており、量子誤り訂正の安定運用や高度なエンタングルメント生成を見据えた設計となっている。
また、ドイツのInfineonと提携し、高精度なトラップ構造の製造技術にも踏み込むなど、ハードウェアの製造基盤においても独自路線を模索している。
このようにQuantinuumは、ハードウェア・アーキテクチャ・応用のすべてを自社内で設計・運用する「フルスタック型」のアプローチをとることで、量子計算の可能性を技術的に担保するだけでなく、商業的な実装へと接続するためのフレームワークを着実に構築しつつある。
Different strokes for different folks:Qubitに首ったけ 気まぐれな“アイツ”と悪戦苦闘の開発者たち C12
パリを拠点とするスタートアップC12は、既存の量子コンピューティング方式とは異なる道を選び、カーボンナノチューブ(CNT)を用いた新しいアーキテクチャの開発に取り組んでいる。その動機は明快だ。「量子誤り訂正の効率を高めるには、個々の物理量子ビットの品質を一定以上に保つ必要がある」。同社CEO、ピエール・デジャルダンはそう語る。
CNTの強みは、ノイズへの耐性と量子状態の保持能力にある。極めて高純度の結晶構造をもち、外部干渉の少ない「静かな環境」を量子ビット単体で実現できるという。これは、エラー訂正の前提条件である「安定した物理ビットの確保」において、他方式とは一線を画す特性だ。いわば、最初から“静かな部屋”で会話できる環境を材料レベルで整える──それがC12の設計思想である。
技術的には、CNT内部に単一電子を閉じ込め、そのスピンや電荷状態を量子ビットとして利用する。このチューブ構造はナノスケールで高密度に配置され、量子状態は超伝導部品と接続された高周波パルスによって制御・読み出しが可能だ。加えて、C12はCNTの製造精度において独自の基盤技術をもち、チップ全体の品質分布を原子レベルでコントロールするという。
2024年には、パリの地下に専用の生産ラインを含む製造拠点を整備。年内には5量子ビットのプロトタイプチップをリリース予定であり、2033年までにはフルスケールの誤り耐性型量子コンピューターの実現を目標に据えている。
CNTという素材がもつ電気伝導性、安定性、スケーラビリティのポテンシャルに賭けるC12の試みは、従来の量子ハードウェアに対する根源的な問いかけでもある。材料の選定から量子計算の設計を起点化する──この方向性が本格化すれば、量子演算という概念自体の定義もまた、更新を迫られることになるかもしれない。